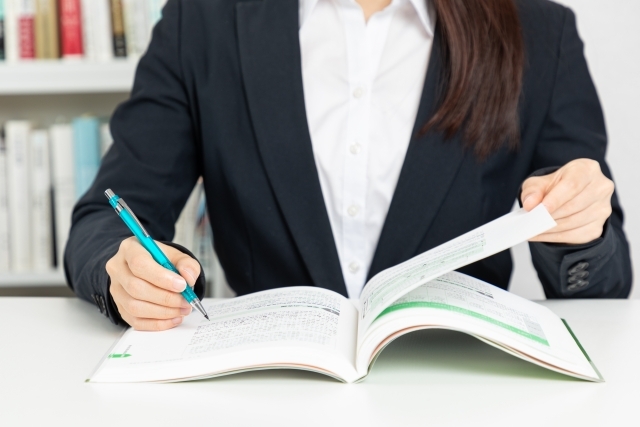本号より数回にわたり企業防災に関するコラムの連載をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
さて一口に企業防災といっても、家具転倒防止対策のような命を守る事前対策から、BCP(事業継続計画)など企業の事業を守る対策まで、様々なメニューが存在します。
ここではそのなかでも、近年わが国の大都市部で精力的に進められるようになってきた「帰宅困難者対策」から解説をしたいと思います。
なお筆者は、現在内閣府で開催されている「災害発生時等の帰宅困難者等対策検討委員会」 の座長をつとめており、国や都道府県の最新の動向も含めた話題提供にしたいと考えております。
さて、東日本大震災をきっかけとして世間で急速に認知が深まったこの対策、そもそも何故このような対策をする必要があるのでしょうか?

大量の帰宅困難者
ご存知のように2011年3月11日に発生した東日本大震災によって、首都圏では515万人ともいわれる数多くの帰宅困難者が発生しました。おそらく、ここまで大量の帰宅困難者が発生した事例は世界初と考えられます。
筆者らが東日本大震災直後に行なった社会調査からは、帰宅が困難になって一番困ったこととして「携帯電話が通じなかった(31%)」が挙げられており、「屋外に長時間いたため体が冷えた(13%)」、「ひとりだったので不安だった(11%)」と続いています。
参考文献 1)
これらの回答を見る限り、この課題は非常時においてそこまで優先度の高いものではなく、何も全国の大都市や事業所がこぞって対策を検討するほどではないように思えるでしょう。
実際、世間では「帰宅困難者対策は元気な人の対策であるため、防災対策としての優先順位は限りなく低い」という誤解に基づいた発言も多々見られます。
確かに、東日本大震災時には大量の帰宅困難者が発生したものの、それによる死者や負傷者は報告されていません。
しかしながらこれは、あくまで揺れが相対的に小さかった東日本大震災時の首都圏に限った話と考えられます。
たとえば首都直下地震や南海トラフ巨大地震が発生して大都市が甚大な被害を受けた場合、多数の建物が倒壊して救急ニーズが増大し、消防力を上回る同時多発火災が発生します。
道路は著しい直接被害を受け多くが不通となり、電気・ガス・水道あるいは電話や携帯電話、インターネットも長期間の不通を余儀なくされるケースが予想されます。
そのような状況下で多数の帰宅困難者が盲目的に一斉帰宅をしてしまうと、彼らが群集なだれや大規模火災に巻き込まれる、あるいは送迎に伴う自動車交通需要の発生がもたらす交通渋滞によって、消防車や救急車などが遅れて被害を拡大させるなど、様々な二次災害が発生・拡大する可能性も否定できません。
さらにこのなかで甚大な津波被害が同時に発生すると、これらの渋滞は避難行動を大きく阻害することも考えられます。
つまり都市が大きく壊れていなかった東日本大震災では帰宅困難者に伴う本質的な問題は顕在化しなかったということができます。
帰宅困難者対策の意義とは
そもそもわれわれは大都市が強い揺れに襲われた場合の対策を検討すべきであり、そのような状況下では大都市で鉄道が運休することに伴う各種混乱や二次被害の発生が懸念されます。そうした事態を防ぐべく、社会全体で一斉帰宅を抑制し、都市内の渋滞をできる限り抑えることで、人的被害に繋がるケースをできるだけ防ごう、という点が帰宅困難者対策の意義となるわけです。
もちろん帰宅困難者対策には、「帰宅手段を失って行き場がなくなってしまった人たちを助ける」というパターナリスティック(温情的)な意義や、避難所運営などと同様に発災直後における行政の負担をできる限り軽減するという意義もあります。
しかしながら、上記のような
| 1.「大都市が大災害時に大混雑する」問題を解決する |
| 2.「帰宅できない」人に対して支援を行なう |
| 3.「行政対応に多大な負荷がかかる」という問題を解決する |
つまり帰宅困難者対策は、企業が行なう防災対策のなかでも「人的被害を減らす」という目的を有する対策であり、企業にとっても「従業員の命を守る」ための対策となります。
それゆえ、企業の規模や種類によらず、帰宅困難者対策が必要であることは言うまでもないでしょう。
たとえば東京都は東日本大震災以降、「従業員の一斉帰宅抑制」、「3日分の飲料水・食料等の備蓄」、「従業員との連絡手段の確保・安全確保」、「駅前や大規模集客施設での利用者保護」などを義務として企業に課すための「東京都帰宅困難者対策条例」 を2012年3月に制定しています。
このように、近年では企業にとって重要となりつつある帰宅困難者対策の具体的なメニューについて、次回以降に企業視点で紹介しようと思います。
参考文献
1) 廣井悠、関谷直也、中島良太、藁谷峻太郎、花原英徳:
東日本大震災における首都圏の帰宅困難者に関する社会調査, 地域安全学会論文集, NO.15, pp.343-353, 2011.