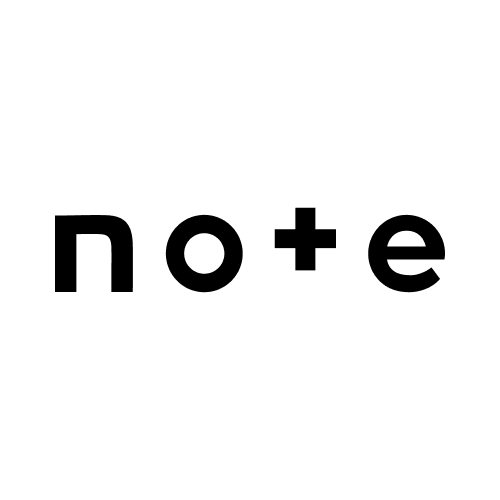ここでしか読めない、専門家独自の目線
税理士や社会保険労務士といった専門家の目を通じて語る連載コラム。タイムリーな話題から、すぐに実務に活かせる内容、企業の管理部門の皆様に知っておいていただきたい情報まで、さまざまな角度から、本誌記事とは違った目線で語っていただきます。
人事労務News&Topics

労務に関する法改正情報などの最新ニュースや、注目の話題をピックアップ。専門家がわかりやすく解説します。
[2025/7/10更新] 2025年6月から義務化! 職場の「熱中症対策」
執筆者プロフィール
SEとして人事系システム開発に従事後、中小企業や上場企業の人事部を経験し、勤務社労士を経て開所。豊富な現場経験を強みに、企業全体の労務リスクを分析し、人事労務DD、IPO支援、人事制度、就業規則の見直し等を行う。現場の声を聞きながら、人事労務セミナーや企業研修講師を行う等、多数の講演実績あり。著書として『労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務』(日本法令)、『IPOの労務監査 標準手順書』(日本法令)など。
小宮弘子氏(特定社会保険労務士)
社会保険労務士が提案する中小企業の「人材・組織マネジメント」

社会保険労務士は日々、顧問先等の人事労務関連について多種多様な質問や相談を受け続けています。その中で最近急速に増えているのが、「人材活用」や「組織のあり方」に関するものです。VUCA(先行き不透明)の時代と言われ始めたところにコロナ禍が直撃したことに加えて、ジョブ型雇用や人的資本経営といった、経営のあり方そのものを大きく変革する事項が政策課題としての具体的な姿を現しつつあります。これらの課題は、日本社会そのもの変革につながるものであるだけに、決して大企業だけが対応すべき問題ではありません。現時点で、中小企業が取り組む価値があると考える人材・組織マネジメントに関する最新の話題について、社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。
[2025/6/30更新] スポットワーク(スキマバイト)を中小企業が利用する場合の注意点執筆者プロフィール
就業規則で会社と従業員はしあわせになれるのか?(連載終了)
サポートクラブ 税務News&Topics(連載終了)サポートクラブ会員限定
中小企業の人材確保を実現する“アフターコロナ”の人事・賃金制度(連載終了)
サポートクラブ 法務News&Topics(連載終了)サポートクラブ会員限定
消費税率アップ(10月1日)前後の取引で想定されるNG集(連載終了)
タックスロイヤーが教える「法人税」のロジック(連載終了)
こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A(連載終了)
ケースと図解で学ぶ 交際費と隣接費用判断のポイント(連載終了)
有給休暇、時間外労働……etc. 働き方改革関連法の概要と実務対応(連載終了)
企業で使える 補助金の申請・活用にまつわる経理実務(連載終了)サポートクラブ会員限定
働き方改革・法改正でやるべき有給休暇管理はこう進める(連載終了)
海外企業との取引はこう進める!トラブルに負けない契約書のつくりかた(連載終了)
高齢社員の働き方への企業対応(連載終了)サポートクラブ会員限定
元総務部長が語る「総務の仕事とは」(連載終了)
間近に迫った無期転換契約のチェックポイントQ&Aサポートクラブ会員限定
中小企業のための 民法(債権法)改正による契約への影響(連載終了)サポートクラブ会員限定
経営管理ツールとしての「月次決算」活用法(連載終了)サポートクラブ会員限定
あなたは大丈夫?意外と知らないビジネスマナーの常識(連載終了)サポートクラブ会員限定
守ろう!あなたの会社のヒト・モノ・情報―中小企業の防災対策(連載終了)サポートクラブ会員限定
-休業から職場復帰まで- メンタル不調者が出たときの労務管理(連載終了)サポートクラブ会員限定
マイナンバー法への実務対応(連載終了)サポートクラブ会員限定
なにわの社労士 井寄奈美の「事例で学ぶ社員の活かし方」(連載終了)サポートクラブ会員限定
税理士・平山憲雄の「最良の経営パートナーにするために!税理士と賢く付き合う方法」(連載終了)サポートクラブ会員限定
弁護士・浅見隆行の「企業コンプライアンスの鉄則」(連載終了)サポートクラブ会員限定