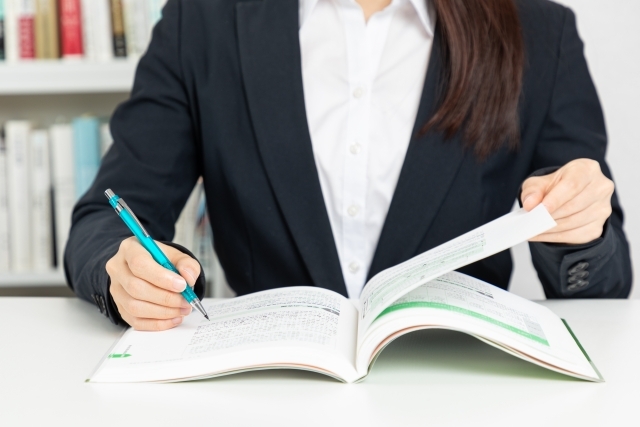本コラムでは、その改正内容と実務上の留意点について解説します。
(1)改正の背景 ― 「見える化」による女性活躍の加速
女性活躍推進法の改正法が2025年6月11日に公布されました。政府は「第5次男女共同参画基本計画」で、2025年までに女性管理職比率30%を目標としていますが、現状では目標に届いていません。
国際的にも、スウェーデン41.7%、アメリカ41.0%、フランス39.9%などに比べ、日本は12.9%と依然として低水準です。
こうした状況を踏まえ、企業における女性活躍を加速させるため、数値の「見える化」と外部への情報開示を推進する仕組みが導入されました。
(2)改正内容
現行制度では、常時雇用する労働者数が301人以上の企業に対し、「男女間賃金差異」の情報開示が義務付けられています。これに対し、2026年4月からは対象範囲が拡大され、常時雇用する労働者数が101人以上の企業についても、情報開示の必須項目として「男女間賃金差異」および「女性管理職比率」の公表が義務化されます。
ここでいう「常時雇用する労働者数」とは、契約社員・パート・アルバイトなどの名称を問わず、継続的に雇用されている労働者全員を指します。
具体的には、
①期間の定めなく雇用されている者
②一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者、または雇入れ時から1年以上雇用が見込まれる者
が含まれます。なお、人数のカウントは「事業所単位」ではなく、企業単位で101人以上であるかどうかで判断されます。
したがって、上場企業・非上場企業を問わず、本社および複数の支店や店舗などを合計した常時雇用労働者数が101人以上である場合には、情報公表義務の対象となります。
(3)情報公表の具体的な項目
2026年4月以降、企業規模に応じて、以下の項目を必ず開示する必要があります。| 企業規模 | 改正前 | 改正後(2026年4月以降) |
|---|---|---|
| 301人以上 | 男女間賃金差異
+ 「①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」のうちから1項目以上を公表 + 「②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」のうちから1項目以上を公表 |
男女間賃金差異
+ 女性管理職比率+ 「①」のうちから1項目以上を公表+ 「②」のうちから1項目以上を公表 |
| 101人以上 300人以下 |
「①」と「②」のうちから1項目以上を公表 |
男女間賃金差異
+ 女性管理職比率+ 「①」と「②」のうちから1項目以上を公表 |
②「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」には、男女の平均継続勤務年数の差、残業時間の状況、男女別の育児休業取得率、有給休暇取得率などが含まれます。
このように、改正後は、101人以上の企業において「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の両方の公表が必須となり、企業の多様性や働き方の実態がより明確に可視化されることになります。
(4)実務ポイント―「管理職の定義」など
新たに公表が義務化される「女性管理職比率」について、「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者を指します。この「課長級」とは、単に役職名で判断するのではなく、職務内容・責任の程度など実質的な権限と役割によって判断されます。
| 【課長級に該当する者の例】 |
|
①事業所で通常「課長」と呼ばれ、2係以上の組織、または構成員10人以上を統括している者 |
|
②呼称、部下数にかかわらず、職務の内容や責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) |
組織構造や職制が複雑な企業では、人事制度上の等級・役割定義と整合させて判断することが重要です。
また、「男女間の賃金差異」については、以前のコラムにて、算出方法を記載していますので、あわせてご確認ください。
≫ 人事労務News&Topics:『「男女の賃金の差異」の情報公表が義務化されました!』
今回の改正により、「女性管理職比率」や「男女間賃金差異」の情報公表が義務化されることは、企業にとって、実態が可視化されるデータが増えるという意味で大きな転換点です。
しかし、真に問われるのは、ただ単に「数値を公表できるか」ではなく、「その数値にどのような意味や背景があり、どのようなストーリーをもって改善していくか」です。
つまり、「改善へのプロセスこそが企業価値を高める鍵」となります。
法改正をきっかけに、組織の実態を見直し、経営戦略と人材戦略を結びつける機会とし、持続的な組織発展へとつなげていきましょう。