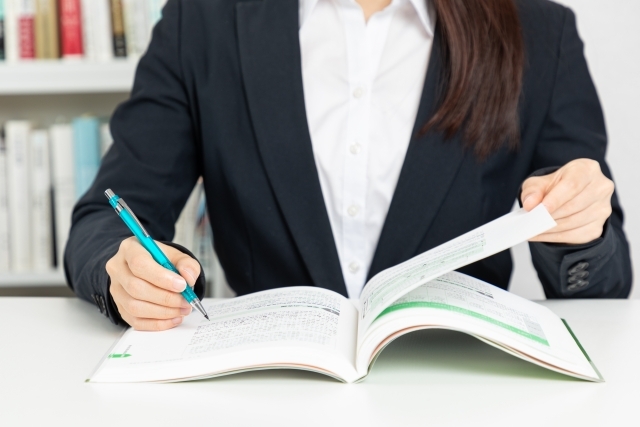本制度は2025年10月に創設されました。
本コラムでは、その具体的な内容について解説します。
(1)「教育訓練休暇給付金」の概要
支給対象者は、以下の①、②の両方の要件を満たす必要があります。①休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
(原則、11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が対象)
②休暇開始前に5年以上、 雇用保険に加入していた期間があること(※)
(過去に、失業給付(基本手当)、教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を受けたことがある場合、通算できない期間が生じる場合がある)
※離職期間があったとしても、12か月以内、かつ、失業給付等を受けていなければ、前後の期間を通算することが可能です。
(2)支給対象となる休暇
支給対象となる休暇は、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。①就業規則等に規定された休暇制度に基づくこと
②労働者本人が教育訓練を受講するために自発的に取得し、事業主の承認を得ていること・休暇は30日以上連続した無給の休暇であること(たとえば、教育訓練休暇中に「数日だけ出勤してほしい」と業務命令を出すことは認められず、連続性が条件となる)
③対象となる教育訓練等であること・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校、各種学校が提供する教育訓練等・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等・職業安定局長が指定する職業に関する教育訓練等(司法修習、語学留学、海外大学院での修士取得等)
(3)給付期間における給付日数など
給付日数は、雇用保険の加入期間に応じて次のように定められています。| 雇用保険に加入していた期間 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
(4)就業規則へ明記するうえでの注意点
教育訓練休暇は、法定外休暇ですので、制度の具体的な内容を会社ごとに自由に決めることができます。教育訓練休暇の制度をつくるうえでは、主に以下の事項を検討するとよいでしょう。
①対象者
対象範囲について、「全従業員とする」「正社員のみなど特定の雇用区分とする」「勤続年数の基準を設ける」などが検討事項となります。当該給付金の支給対象者は、雇用保険の加入期間が5年以上あることが要件ですので、たとえば、「勤続年数5年以上の正社員を対象とする」と規定することが考えられます。
②休暇の取得期間
「休暇の取得期間に上限を設けるか」「休暇の分割取得を認めるか」などが検討事項となります。当該給付金の支給対象となる休暇は、30日以上連続した休暇であることが要件ですので、たとえば、「休暇の取得期間は、30日以上6か月未満とし、連続取得すること」と規定することが考えられます。
③勤続年数への算入
休暇の取得期間について、年次有給休暇の付与要件とする勤続年数や、退職金算定の勤続年数などに算入するか否かが検討事項となります。④給与、賞与の取扱い
休暇取得時の給与の支給の有無、賞与算定への影響が検討事項となります。当該給付金の支給対象となる休暇は、無給の休暇であることが要件ですので、たとえば、「休暇取得時の賃金は、無給とする」「賞与の算定対象期間としては、対象外とする」と規定することが考えられます。
教育訓練休暇給付金は、従業員が安心して学び直しに専念できるよう支援する制度です。
一時的な教育訓練休暇を、企業全体の競争力向上や定着率アップにつなげる「組織戦略」として捉えることも有効ではないでしょうか。