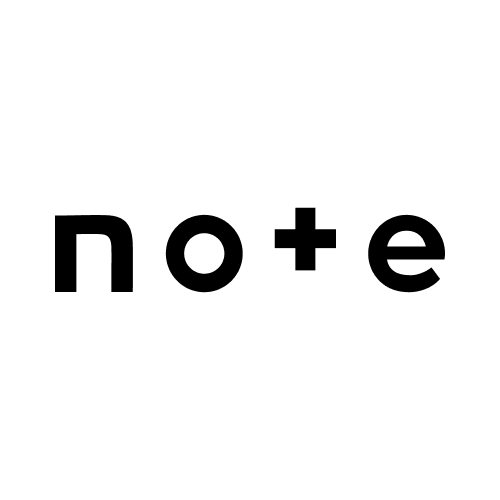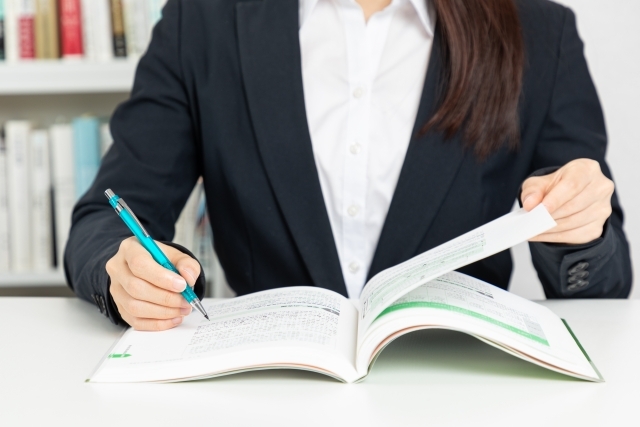本コラムでは、中小企業の「人材・組織マネジメント」についてお伝えしています。
ここ数回は、オンボーディングやアルムナイなど、人材採用に関する話題を続けてお届けしてきました。
今回はさらに進んで、採用も含めた「人への投資」に関する重要な指標である「人的資本ROI」についてお伝えします。
1.人的資本ROIとは?
人的資本ROI(Human Capital Return on Investment)とは、企業が「人への投資」から得られる利益(収益率)を評価するための指標です。ISO(国際標準化機構)が定めた人的資本に関する情報開示のガイドラインである「ISO30414」では、人的資本ROIの計算式を「(売上高-人件費を除く経費)÷人件費-1」としています。
これにより、人件費によって生み出された価値、つまり「人への投資」が生み出した価値を把握することができます。
ここに登場する「人件費」とは、企業が事業を遂行するうえで従業員にかかるすべての費用をいいます。
給与や賞与、退職金だけでなく、法定福利費や福利厚生費、そして教育研修費などが含まれます。
給与や賞与も「人への投資」の1つなのですが、やはり「人への投資」といえば教育研修費(教育訓練費)が中心的な存在でしょう。
ここでは、営業部の従業員に対して教育研修費を投じたケースを例としましょう。
外部コンサルタントに依頼して、新たな営業手法やDX(デジタルトランスフォーメーション)対応に関する研修を、営業部の従業員に対して行なってもらったとします。
人的資本ROIを算出することによって、このような教育研修が売上にどの程度貢献しているかを数字で把握することができるのです。
教育研修によって営業効率が改善され、新規受注が増え、その結果売上が増大したというような場合に、どのくらいの「人への投資」でどのくらいの利益を得られたのかがわかるということです。
2.人的資本ROIと中小企業の人材・組織マネジメント
人的資本ROIという指標は、大企業はもちろんのこと、中小企業にとっても重要です。むしろ、中小企業こそが積極的に活用すべきと考えます。
なぜかといえば、豊富な人員に裏付けられた組織力によってパフォーマンスを出せる大企業と違って、中小企業は個々の人材のパフォーマンスに大きく左右される部分が大きいからです。
新たな人材の獲得や育成も、既存の人材の活用も、従業員一人ひとりにどのような働きかけをし、個人の意欲や成長を促せたかが、そのまま中小企業の業績に直結します。
つまり、「人への投資」とそのリターンが把握しやすい土壌があるのです。
「人への投資」つまり人材戦略を経営戦略に位置付けるのが、近時注目されている人的資本経営です。
人的資本経営は大企業が先行して取り組んでいる面がありますが、中小企業にとっても決して高いハードルではありません。
今までも行なっていた、人材獲得や人材育成について、「投資」という観点から改めて見つめ直し、適切に改善していけばよいのです。
見つめ直しのきっかけとなる、「人への投資」再検討リストを次に掲げます。
【「人への投資」再検討リスト】
| (1) | 採用活動に適切な人員と費用を投じているか |
| (2) | オンボーディングを意識して行なっているか |
| (3) | 研修システム(OJT・Off-JT)を計画的に整備し、必要な費用を投じているか |
| (4) | 資格取得の費用助成やリスキリング支援制度を構築しているか |
| (5) | 働きやすい職場づくり(健康経営・ハラスメント防止など)をしているか |
| (6) | ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)に配慮しているか |
| (7) | 労働法(時間外・休日労働の規制や有給休暇の取得など)を遵守しているか |
| (8) | 多様性(ダイバーシティ)や包摂(インクルージョン)に配慮しているか |
| (9) | 心理的安全性の確保と対話の実践を心がけ、適切な人事評価を行なっているか |
| (10) | 評価や物価上昇(インフレ)に対応した、適切な賃金を支給しているか |
そして、再検討リストに列挙されたことのほとんどが、本コラムでこれまで解説してきたことです。
ぜひ、過去のコラムも参照されつつ、この再検討リストを活用し、「人への投資」のリターン向上につなげていただきたいと思います。
3.「見える」結果と「見えない」結果の両方に配慮を
人的資本ROIなど、ISO30414で採用されている指標は、自社の人的資本経営を「見える化」するためのものです。数字で表せるものには説得力がありますし、1年、3年、5年と経年で変化を追いやすいメリットがあります。
しかし、「見える」結果を追うだけでは、中小企業の人材・組織マネジメントとしては不十分です。
それは本コラムをお読みの経営者や人事労務担当者の方々がよくご存じのことだと思います。
モチベーションやエンゲージメントなどの主観的な要素も数値化して定量的に把握できるようにはなっていますが、職場の雰囲気や顧客との関係性、さらには従業員が抱えている仕事や私生活に関する個人的な悩みなどについてはそうはいきません。
ですが、その「見えない」結果もまた、「人への投資」によって改善向上できるものです。
具体的な方法としては、再検討リストの(9)にある心理的安全性の確保や対話の実践が挙げられます。
これらについても、管理職研修を定期的に実施し、そのメニューにコーチングやアンガーマネジメント、ハラスメント対応などを組み込むなど、費用を投じる必要があります。
また、管理職が対話に費やした時間も人件費が投じられたことになります。
これらの施策は、結果的に人的資本ROIで把握することも可能になります。
「見える」結果と「見えない」結果の双方に注意しつつ、「人への投資」のリターン向上を目指して、人材・組織マネジメントをさらに進めていただきたいと思います。