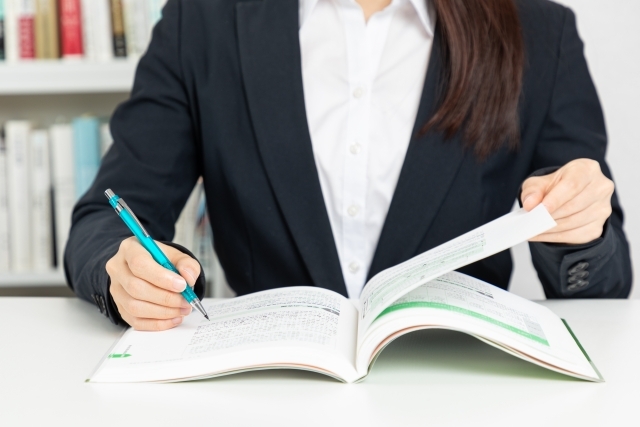国内企業間の取引では、その是非は別として、契約書を作成せず発注書のみで取引を行ったり、よく内容を検討せずに契約書を作成してしまったりということがしばしば見受けられます。
しかし、海外企業と取引する場合には、思いもよらなかったトラブルにつながるおそれがあります。それでは、どのようなトラブルが想定されるでしょうか。
しかし、海外企業と取引する場合には、思いもよらなかったトラブルにつながるおそれがあります。それでは、どのようなトラブルが想定されるでしょうか。
【ケース1】
日本企業J社は、ベトナム企業V社との間で、自社製品に使用する部品xをV社に製造させ、購入することになりました。
契約書や仕様書を作成しないまま発注書のみで取引を始め、J社は部品xを継続的に購入していましたが、ある時、10か月前に納入された物に、品質不良が存在することが判明しました。
J社は、V社に対し、代替品の納入と損害賠償を求めましたが、V社は、「J社が主張する点は品質不良とはいえないし、J社での検収にも合格している。今さら10か月前に納入した物について言われても、そのような責任を負う合意もしていないし、応じられない」として、いっさい取り合いませんでした。
契約書や仕様書を作成しないまま発注書のみで取引を始め、J社は部品xを継続的に購入していましたが、ある時、10か月前に納入された物に、品質不良が存在することが判明しました。
J社は、V社に対し、代替品の納入と損害賠償を求めましたが、V社は、「J社が主張する点は品質不良とはいえないし、J社での検収にも合格している。今さら10か月前に納入した物について言われても、そのような責任を負う合意もしていないし、応じられない」として、いっさい取り合いませんでした。
【ケース2】
日本企業J社は、もともと日本国内で製造・販売していた商品yを、本国での販売を希望する米国企業U社に対し、販売することになりました。
J社は、「日本向けの商品yが、米国での知的財産権を侵害していないかは保証できない」とU社の担当者に伝えており、メールで承諾も得ていました。
取引を開始するにあたり、U社から、英文の契約書の案を受領しました。J社では、英語ができる従業員に翻訳させてみたものの、難解であったため、結局よくわからないまま契約を締結してしまいました。
米国で商品yを販売したところ、別の米国企業A社から特許権侵害を理由に損害賠償請求を受け、U社は多額の支払を余儀なくされます。そこでJ社に対し、「A社への支払について補償を請求する。カリフォルニア州裁判所に訴訟を提起することも辞さない」という通知を行いました。
J社が慌てて弁護士に相談すると、契約書に、「第三者の知的財産権侵害を理由にU社が損害を被った場合には、J社が一切の損害を補償する」「カリフォルニア州裁判所を管轄裁判所とする」という内容や、「完全合意条項」(※)が存在することが判明しました。
弁護士からは、「『完全合意条項』も存在するため、事前にU社の担当者から得ていた承諾のメールを根拠に争うことは難しい。米国での訴訟はリスクが大きいため、多額の損害賠償を支払って和解することも検討する必要がある」と言われました。
J社は、「日本向けの商品yが、米国での知的財産権を侵害していないかは保証できない」とU社の担当者に伝えており、メールで承諾も得ていました。
取引を開始するにあたり、U社から、英文の契約書の案を受領しました。J社では、英語ができる従業員に翻訳させてみたものの、難解であったため、結局よくわからないまま契約を締結してしまいました。
米国で商品yを販売したところ、別の米国企業A社から特許権侵害を理由に損害賠償請求を受け、U社は多額の支払を余儀なくされます。そこでJ社に対し、「A社への支払について補償を請求する。カリフォルニア州裁判所に訴訟を提起することも辞さない」という通知を行いました。
J社が慌てて弁護士に相談すると、契約書に、「第三者の知的財産権侵害を理由にU社が損害を被った場合には、J社が一切の損害を補償する」「カリフォルニア州裁判所を管轄裁判所とする」という内容や、「完全合意条項」(※)が存在することが判明しました。
※完全合意条項・・・契約書に記載された内容がすべてであり、それ以前の合意は効力を有しないことを示した条項(詳しくは次回、ご紹介します)
【ケース3】
日本企業J社は、中国企業C社から注文を受け、C社特注の製品zを製造・販売することになりました。
J社は、市販の英文契約書の雛形を使用し、代金支払期日は製品の検収完了後、管轄裁判所は東京地裁と定め、契約書を作成して、契約を締結しました。
その後、J社は、注文通りに製品zを製造し、C社に納入したはずなのですが、C社は、納入された製品が仕様を満たしていないと主張して、代金の支払を拒みました。しかし、C社が主張する内容は合意された仕様に含まれていません。もしかすると本当は、C社の経営状態があまり良くないための言いがかりかもしれません。
J社は、代金の支払を求める訴訟を提起することも視野に、弁護士に相談しました。
しかし、弁護士からは、「東京地裁に訴訟を提起しても、中国では強制執行できないおそれがあることなどから、意味をなさない可能性も十分にある」と言われてしまいました。
J社は、市販の英文契約書の雛形を使用し、代金支払期日は製品の検収完了後、管轄裁判所は東京地裁と定め、契約書を作成して、契約を締結しました。
その後、J社は、注文通りに製品zを製造し、C社に納入したはずなのですが、C社は、納入された製品が仕様を満たしていないと主張して、代金の支払を拒みました。しかし、C社が主張する内容は合意された仕様に含まれていません。もしかすると本当は、C社の経営状態があまり良くないための言いがかりかもしれません。
J社は、代金の支払を求める訴訟を提起することも視野に、弁護士に相談しました。
しかし、弁護士からは、「東京地裁に訴訟を提起しても、中国では強制執行できないおそれがあることなどから、意味をなさない可能性も十分にある」と言われてしまいました。
ケース1~3におけるトラブルの原因
ケース1~3では、J社には以下の問題点があったために、トラブルを回避できなかったと考えられます。
次回以降、これらのケースを解説しながら、海外企業との契約トラブルを回避するにはどうしたらよいか、そのポイントをご紹介していきます。
ケース1:文化・商習慣の違い等があるにもかかわらず、部品xの仕様を書面で合意せず、相手側が負う責任の内容や期間も定めなかったこと
ケース2:「完全合意条項」の意味や、海外の裁判所での訴訟のリスクを意識しないまま、契約書を作成したこと
ケース3:契約書において、代金不払に対処する方法を確保しておらず、異国間での紛争解決方法も適切に選択していなかったこと