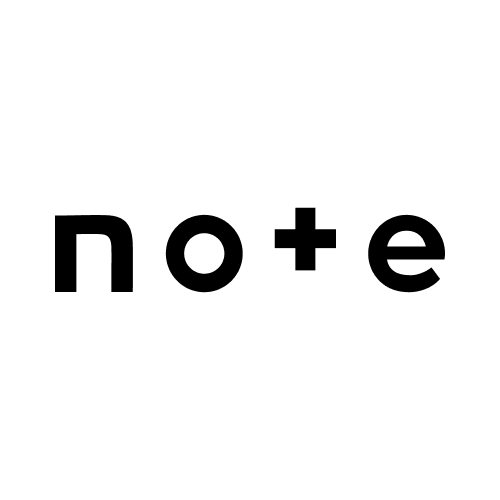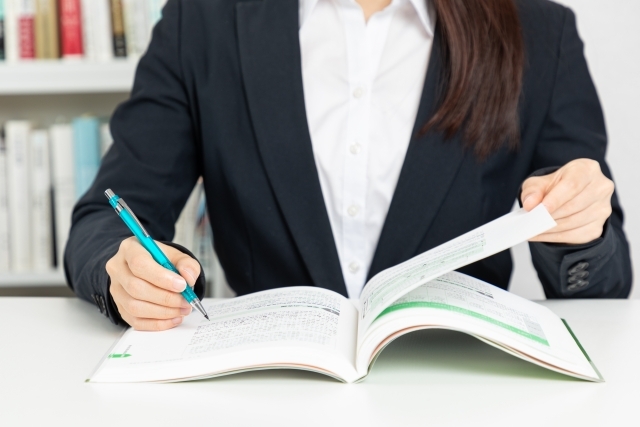ここ数回は、オンボーディングやアルムナイなど、人材採用に関する話題を続けてお届けしてきました。
今回は人材採用だけでなく、人材維持にもかかわる「高齢者雇用」についてお伝えします。
1.高齢者雇用の現状は?
本コラムで数多くご説明してきた「人的資本経営」は、人材戦略を経営戦略に位置づけ、「人への投資」を行なうことで企業価値を向上させるという基本的な考え方に基づく経営のあり方です。その「人」には、さまざまな人がいます。
各企業の「人的資本レポート」などに目を通していると、女性活躍や外国人雇用についてはかなり取り上げられていますが、高齢者の活用についてはそれほどでもないという印象を受けます。
人的資本経営の国際的ガイドラインであるISO30414でも、「労働力のダイバーシティ<年齢>」という項目こそあれ、高齢者に関して特に焦点を当てた項目というのは現状ではありません。
しかし、「人生100年時代」といわれる今、労働力としての高齢者にはもっと積極的な目を向けられるべきだと考えます。
2025年(令和7年)6月10日に公表された内閣府「令和7年版高齢社会白書」(以下「白書」)によると、令和6年(2024年)の労働力人口6,957万人のうち、65歳から69歳までの人は400万人とのことです。
さらに、70歳以上の労働力人口が546万人ですので、労働力人口に占める65歳以上の高齢者の割合は13.6%に達しています。
高齢者の割合は長期的に上昇傾向にあるということですが、今や10人に1人以上の割合で高齢人材が活躍しているということは、人材・組織マネジメントにおいて強く意識されるべき事柄です。
2.人生100年時代の「働き方」とは?
今回はもう少し数字を見てみましょう。白書によれば、60代後半の男性の6割以上、女性の4割以上が就業しているそうです。
そして、現在収入のある仕事をしている60歳以上の人のうち、約3割が「働けるうちはいつまでも」働きたいという意欲を示しています。
リンダ・グラットンが著書「LIFE SHIFT」において「人生100年時代の人生戦略」について考えることを唱えました。
その中で、これまで主流だった「学生→働く→老後」という人生の「3ステージ型」から、「マルチステージ型」の人生へと移行していく未来像を提示しています。
マルチステージ型とは、人生(LIFE)のキャリア全体を通じて、その時その時の本人だけでなく家族の事情を踏まえて、生き方や働き方を見直していくライフスタイルのことです。
前述の「働けるうちはいつまでも」という意欲は、「学生→働く→老後」の3ステージのうちの「老後」というキャリアを意識しない人生のあり方を意味します。
このあり方は、リンダ・グラットンのいう「マルチステージ型」への移行の前触れではないでしょうか。
そうなると、「人生100年時代の働き方」について真剣に考えるべき時期が到来したといえます。
3.人的資本経営のKPI設定としての「高齢者雇用」
本コラムでは、人的資本経営のKPI(※)設定の例として、「健康経営優良法人」「くるみん」「えるぼし」をご紹介しました。「人生100年時代の働き方」を考えた人的資本経営を行なう場合にもKPI設定をするべきでしょう。
(※)Key Performance Indicator(重要業績評価指標):組織の目標達成のための指標。この指標を定めることで、目標と現状の差を把握しつつパフォーマンスの改善・向上を図るもの。
≫ 連載第23回:『「人的資本経営」におけるKPI設定 その①』≫ 連載第24回:『「人的資本経営」におけるKPI設定 その② 「健康経営優良法人」を目指して』
≫ 連載第25回:『「人的資本経営」におけるKPI設定 その③ 「くるみん」認定を目指して』
≫ 連載第26回:『「人的資本経営」におけるKPI設定 その④ 「えるぼし」認定を目指して』
高齢者雇用については、まず「健康経営」を基本に据えたうえで、各企業の実情に合わせてKPIとなるべきものを考えていくことをお勧めします。
筆者は、高齢者雇用に取り組む企業に対し、次のような視点を持って人材・組織マネジメントがなされているかチェックすることをお勧めしています。
| (1) | 社内のあらゆる点を「高齢者の視点」で見直してみる |
| (2) | 高齢者にとって肉体的・精神的・時間的にゆとりある環境を確保する |
| (3) | 新技術(HRテクノロジー・AIなど)について高齢者向けの説明を工夫する |
| (4) | 高齢社員とその他の社員との世代間ギャップに配慮する |
| (5) | 高齢者の労働災害防止に向けた措置を講じる |
折しも、労働安全衛生法の改正により、2026年(令和8年)4月から「高齢者の労働災害防止のための措置」が努力義務化されることになりました。
努力義務ではありますが、厚生労働大臣からこの措置の実施のための指針(ガイドライン)が出される予定ですので、この指針もぜひ活用したいところです。
高齢者雇用に関する独自のKPIを設定することで、「働けるうちはいつまでも」という意欲ある人に「マルチステージ型」の人生の働き場所として選んでもらえるような職場づくりをぜひ達成してください。