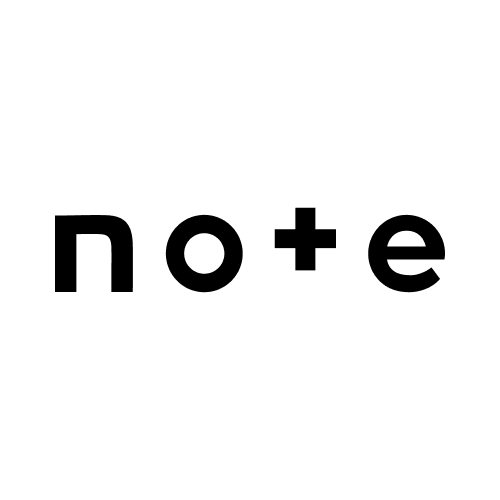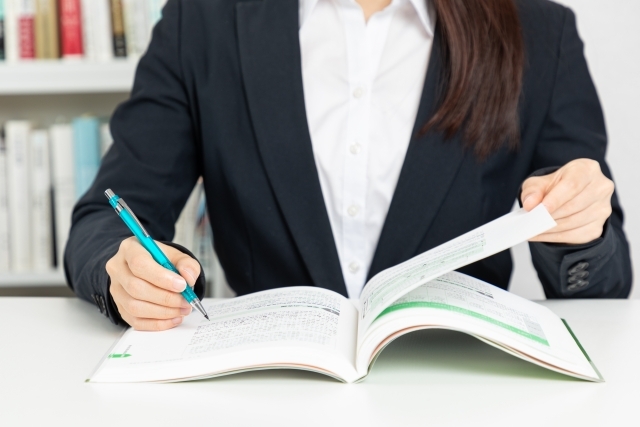今回は新卒社員に関するオンボーディングの実践についてです。
1.新卒社員の早期離職を防ぐために
オンボーディングは早期離職の防止や能力発揮を目的として行なわれるものでした。この春も4月の入社後3日目の段階で早くも、「退職代行業者から新卒社員の退職の連絡が来た!」というようなケースを耳にします。
退職の理由はさまざまですし、新卒社員の場合は「3日、3月、3年」と言われるように、早期の段階で一定の離職が生じることは半ば常識化している面もあります。
それでも、退職理由が何らかの「ミスマッチ」によるものならば、オンボーディングの実践の仕方によっては防げたかもしれないのです。
「早くも」と書きましたが、実は4月は早い時期ではないのです。
どういうことかと言えば、オンボーディングは通常、入社前研修(内定者研修)から行なうものですが、それよりももっと早い段階から意識して行なっていれば、時間や費用、そして手間をかけて採用に至った人材を入社直後に失うことを避けられた可能性があるからです。
企業側の視点で言うならば、「もっと早く言ってほしかった……」、よりはっきり言えば「内定後早めに辞退してくれれば、他の人を採用できたのに……」と思うこともあるでしょう。
その意味でも、4月は早い時期ではないのです。
2.「初期キャリア管理」としてのオンボーディング
「初期キャリア管理」という人材・組織マネジメント上の用語があります。これは、募集・内定・採用・配属といった入社前後の管理を意味するものですが、オンボーディングは初期キャリア管理の1つの方策であり、だからこそ募集段階から行なってほしいのです。
「初期キャリア管理」は就職戦線の前倒しが進む傾向のなかで、その幅が広がっているのです。
筆者は社会保険労務士として、新卒者に限らず労働条件に関する各企業の相談を受けたり、労務監査(労務デューデリジェンス・労務DD)において労働条件通知書や雇用契約書の適法性のチェックを行なったりしています。
ですが、労働条件以外についても、重要な要素は多々あります。
たとえば、同じ1日8時間労働であっても、職場の雰囲気や求められるパフォーマンスのレベルなどは企業によって多種多様です。
「ミスマッチ」は、まさに「契約書からは見えない」部分で生じるものなのです。
3.リアリスティック・ジョブ・プレビュー(RJP)とは?
リアリスティック・ジョブ・プレビュー(RJP)という理論があります。直訳すると「現実的職務予告」という、こなれない日本語になってしまいますが、企業は求職者に対して、自社のプラス面(ポジティブな面)だけでなく、マイナス面(ネガティブな面)も開示したほうが良いという考え方です。
アメリカの産業心理学者ジョン・ワナウスが1970年代半ばに提唱したものですが、日本でも最近、人材・組織マネジメントにおいて普及しつつある考え方となっています。
RJPには次の表にあるとおり、4つの効果があるとされます。
| ①セルフ・スクリーニング効果 | 企業のリアルな情報開示を受けることで、求職者自身が適合性を正確に判断できる効果 |
| ②ワクチン効果 | ネガティブ情報に事前に接することで、入社後のリアリティ・ショックを回避もしくは緩和できる効果 |
| ③コミットメント効果 | 正確な情報を開示する真摯な姿勢に接することで、企業に愛着を持ってもらえる効果 |
| ④役割明確化効果 | 企業が入社後のキャリアプランを明確にすることで、その期待に応えたいという意欲を高める効果 |
昔から「5月病」という言葉があるとおり、「理想と現実の不一致」による失望(リアリティ・ショック)は早期退職の原因となりますが、RJPはそれに対する免疫を事前につける効果があります。
③は、企業説明会や面接の場で、企業がネガティブ情報についても臆さず開示することが、かえって企業の信用性を増すことになる効果です。
④は、求職者の希望にどのタイミングでどのように応えられるかを明確にすることで、入社直後に希望と違った部署に配属されても、モチベーションの低下を招かないなどの効果が期待できるということです。
この観点からも、本連載で以前お伝えした「人材年表」を作成しておくことで、自社の「数年後」を意識しての採用であるというアピールが可能になります。
≫ 連載第1回:『自社の3年先、5年先は? 「人材年表」の活用による、先回りした人事労務管理』参照
そして、①ですが、企業はついつい自社の良いところばかりを求職者に見せようとしてしまいます。
しかし、現代は就活関連の口コミサイトも充実し、SNS上でも企業の実態に関する情報が満ち溢れています。
つまり、企業がネガティブ情報を開示しなくても、求職者はある程度情報収集できてしまうわけです。
それならば、ありのままの姿を開示したほうが、かえって信用度が増すだけでなく、「それでも自分はこの企業で働く」という決意を固めてくれた人材なので、離職する可能性が低くなる効果も期待できるということです。
すでに、就活生に対する大学のキャリアガイダンスなどでは、「ネガティブ情報を開示しているか否かも企業選びのポイント」だと伝えていたりしますので、その意味でも、募集時に美辞麗句を並べるだけでは意味がなくなりつつあります。
人的資本経営とは、人材への投資を経営戦略に位置づけることですが、正確な情報の提供も1つの「投資」だとお考えください。
RJP理論は、新卒社員だけでなく、中途採用社員の初期キャリア管理にも適用できます。
ぜひ、募集段階から求職者に関する情報開示をすることもオンボーディングの実践だという意識を持っていただきたいと思います。