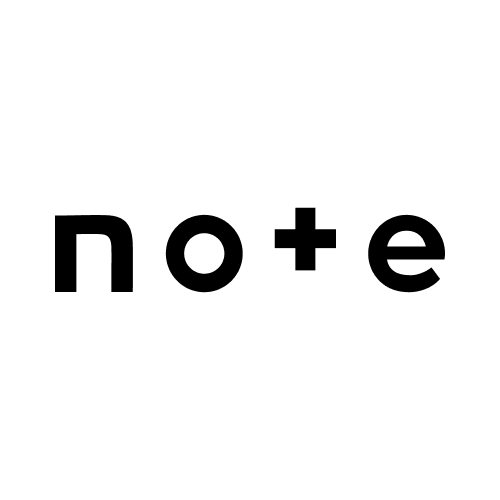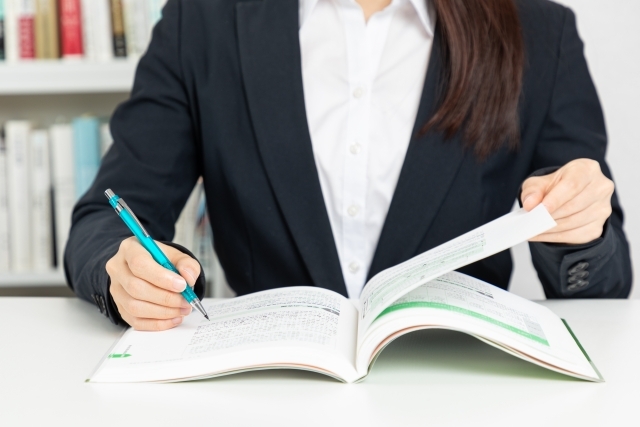1.アルムナイとは?
アルムナイ(alumni)とは、「卒業生」「同窓生」を意味する英語です。この「アルムナイ」を人材・組織マネジメントの領域で使用すると、「(自社の)中途退職者」という意味になります。
中途退職者というのは、通常は定年退職者を含まずに使われているからです。
アルムナイが注目されている理由は主に2つです。
1つは新たな採用のあり方として、もう1つは社外ネットワーク構築手段です。
それぞれについて解説します。
2.採用手段としての「アルムナイ採用」
(1)「アルムナイ採用」とは?
「アルムナイ採用」とは、自社を中途退職した人材を再雇用する採用手法です。かつては、自社を退職した人材とは、それで縁が切れてしまうことがほとんどでした。
今よりも長期雇用(終身雇用)制度を中核とする日本型雇用システムが強く機能していた時代においては、入社した企業で定年まで勤め上げることが半ば常識化していたこともあり、企業側からすると、極端に言えば「中途退職者は裏切り者」という受け止め方をしていた面もありました。
しかし、日本型雇用システムが変容し、働き方が多様化したことに加えて、人手不足が深刻化したなかで、企業の中途退職者への見方も変容していったのです。
また、中途退職者側も世の中が「オープンなキャリア観」を受容するようになるとともに、元の所属企業に復帰するというキャリア形成のあり方を現実的なものとして考えるようになりました。
端的に言えば、使用者、労働者が共にアルムナイ採用のメリットに気づいたということです。
本コラムは中小企業の人材・組織マネジメントに関するものですので、企業側から見たアルムナイ採用のメリットとデメリットを整理してみます。
(2)「アルムナイ採用」のメリット・デメリット
企業側から見たアルムナイ採用のメリット・デメリット| メリット | (1)企業文化や業務プロセスへの理解があり、即戦力として期待できること |
| (2)採用コスト・教育コストの削減が期待できること | |
| (3)退職後に得た知識やスキル、人脈の活用が期待できること | |
| デメリット | (1)過去の退職理由が再度問題化するリスクがあること |
| (2)受け入れる側の従業員が歓迎しないリスクがあること | |
| (3)労使双方の「期待」にミスマッチが生じるリスクがあること |
(1)は、特に退職前に担当していた業務であれば、採用後に即戦力として活躍してもらうことが期待できます。
これは他の採用方法にはないメリットといえるでしょう。
(2)は、採用・教育共にアルムナイの人柄・知識・スキルなどについて十分に把握できていることから、コスト面の削減が期待できるというメリットです。
さらに(3)ですが、退職前に保有していた能力だけでなく、退職後に社外で得た知識やスキル、人脈の活用も期待できるというメリットもあります。
デメリットの(1)は、「そもそもなぜ一度退職したのか」という根本的な問題に関係するものです。
家庭の都合等のやむを得ない理由ならばともかく、たとえば企業側の待遇面・人材配置面などが不服で退職したというような場合では、アルムナイ採用後に同様の問題が起き、「再炎上」するリスクがあります。
(2)は、アルムナイ人材を自社の従業員が快く迎えてくれるとは限らないということです。
かつて退職時に引き継ぎを十分にしていなかった等の事情で、受け入れる側が悪感情を抱いている可能性もあるからです。
(3)は、企業側は「アルムナイ人材がかつて有していた能力・知識」を前提に「期待」をして採用するわけですが、その能力・知識が保たれているとは限りません。
それだけでなく、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の進展や職場の人材の入れ替わりで、かつてとは環境が変わっている場合、従前の能力・知識が活用しにくくなってい
る可能性もあり得るのです。
これを裏返しにすると、アルムナイ人材側も「かつて働いていた環境」を「期待」して入社したところ、かなりのギャップが存在し、そこに苦しむリスクがあるということです。
(3)「アルムナイ」を組織内で再び活用するために
アルムナイ採用は、3つの「期待」と3つの「リスク」があることをお伝えしました。たしかにアルムナイはかつて自社に所属していた人材だからこそ、即戦力としての「期待」も高いですが、「リスク」も同時に存在します。
では、アルムナイを組織内で再び活用するためにはどうしたらよいのでしょうか?
本コラムで「オンボーディング」について3回にわたってお伝えしました。
その際に、中途採用人材については「組織再社会化」のプロセスを経る必要があることをご説明しました。
このことは、かつて自社に所属していたアルムナイであっても変わりはないのです。
「アルムナイだから特に説明や配慮はいらないだろう」という思い込みは禁物です。
組織に「なじむ」ためのプロセスをしっかりと用意しなければなりません。
そのためには、アルムナイがなぜ自社に復帰することになったのかを職場のメンバーに説明することで心理的安全性を確保するとともに、アルムナイにも一度「アンラーニング」(以前の知識やスキルを意図的に棄却しながら、新しい知識・スキルを取り入れるプロセス)をしてもらう必要があります。
アルムナイを迎え入れるメンバーは「お手並み拝見」という態度になりがちです。
そのような雰囲気のなかではアルムナイも孤独感・孤立感に苛まれてしまい、期待された能力を発揮できなくなってしまいます。
それを防ぐためには人材・組織マネジメントをする側が、従来のメンバー、アルムナイの両者と丁寧な「対話」をしなければなりません。
メンバーには、なぜ自社にアルムナイの復帰が必要なのかと、復帰がメンバーの利益にもなるということを、丁寧に「対話」で伝えてください。同時にアルムナイには、復帰後最初の課題が「自己の再定義」であることと、そのためにメンバーと「なじむ」必要があることを、しっかり「対話」で伝えてください。
心理的安全性の確保とアンラーニングの実践が車の両輪のように機能することで、アルムナイが活躍する素地ができあがっていくのです。
3.社外ネットワーク構築手段としての「アルムナイ」
アルムナイが注目されているもう1つの側面が、「社外ネットワーク構築手段」です。退職後もアルムナイと良好な関係を保ち続けることで、自社の商品・サービスを社外に伝えてくれる役割を果たしてもらえたり、新たな取引先や人材を紹介してもらえたりすることが期待できます。
また、アルムナイは自社の内情をよく知っているだけに、退職後にコミュニケーションを取ることで、自社の現状について率直な意見やアドバイスを得ることができるかもしれません。
もっとも、アルムナイを社外ネットワークとして十全に機能させるためには、在職時から良好な関係を築いておく必要があります。
その意味で、人的資本経営(経営戦略と人材戦略を連動させる経営のあり方)、人材・組織マネジメントは、やはり何よりも重要だといえるでしょう。