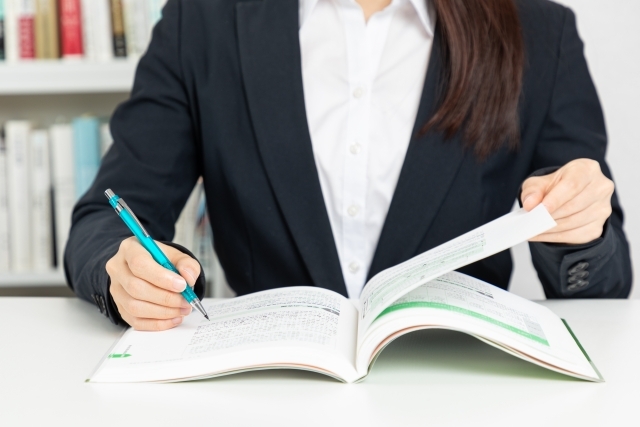そこで今回は、在宅勤務における労災保険の取扱いについて解説していきます。
そもそも、在宅勤務において、労災保険の適用はあるのでしょうか。
A:労働者として在宅勤務を行なっている場合、業務上の災害として労災保険の適用対象となります。ただし、一定の要件を満たした場合に限られます。
(1)労災保険の対象として認められる要件
まず前提として、労働者のケガ等が業務上の事由と認定されるためには、次の2つの要件を備えていることが必要です。・業務遂行性…事業主の支配下にあること
(労働者のケガ等が、仕事を行っていた時に起きたこと)
・業務起因性…事業主の支配下にあったこととその負傷との間に因果関係があること
(仕事が原因となって、従業員がケガ等をしてしまったこと)
(2)在宅勤務における労災認定
厚生労働省では、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(以下、「ガイドライン」)において、在宅勤務時の留意点として、「私的行為等業務以外が原因であるものについては、業務上の災害とは認められない」としています。つまり、在宅勤務における労災認定では、労働者のケガ等が、就業中に、仕事(私的行為等除く)が原因で起きたことを証明できることが、求められることになります。
しかし、在宅勤務では事実確認が難しいため、運用においては工夫が必要となるでしょう。
「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000545678.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000545678.pdf
(3)労災認定される具体的な事例・運用ポイント
ガイドラインでは、労災認定されるケースとして下記のような事例を示しています。「自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くために作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した。」
この事例から運用上のポイントを考えてみたいと思います。
1. 所定労働時間に何をしていたのか
所定労働時間といっても、在宅勤務ゆえに、労働時間の中(休憩時間を除く)で”少し洗濯物を干そう”など、私的な行為が簡単にできてしまいます。したがって、労務管理としては、このような「私的時間」なのか、「労働時間」なのかを明確に区別していくことが重要になります。しかし、「私的行為をしないでください」と会社が労働者に伝えても、在宅勤務のため限界がありますので、上手く管理していくために、「私的時間」と「労働時間」とを区別する仕組みを作ることもひとつです。例えば、勤怠システムなどによって、中抜け時間のこまめな管理を行なったり、在席・離席情報の管理システムを導入したりするのも良いでしょう。2. 仕事を行なう場所であったのか
上記の事例では、「作業場所に戻り」とありますので、仕事を行なう場所が自宅の中でも明確になっていることが読み取れます。一方、筆者のもとには、先日こんな相談がありました。
「長引く在宅勤務のストレスのせいなのか、労働者が勝手にカフェに行って仕事をしている」
このような場合には、在宅勤務者がカフェで転倒しても、就労場所ではないため、労災認定は難しいでしょう。
したがって、運用上のポイントとしては、自宅の作業場所がどのような環境になっているのか申請をしてもらい、会社がそれを把握しておくことが大切になります。例えば、在宅勤務申請の際に作業環境の図を記入してもらうなど、申請書を工夫するのも良いでしょう。また、申請書の提出をルールにするためにも、テレワーク規程等に根拠条文を設けておくことも重要です。
これからの時代、在宅勤務は特別なことではなく、一般的な働き方となる時がもうすぐそこにあると感じられます。会社も労働者も気持ちよく在宅勤務を行なうために、決めておく事項はルール化しておくことが大切です。今からでも遅くはないでしょう。
本コラムも参考にしていただき、在宅勤務体制を強化していただくのも良いかもしれません。
本コラムも参考にしていただき、在宅勤務体制を強化していただくのも良いかもしれません。