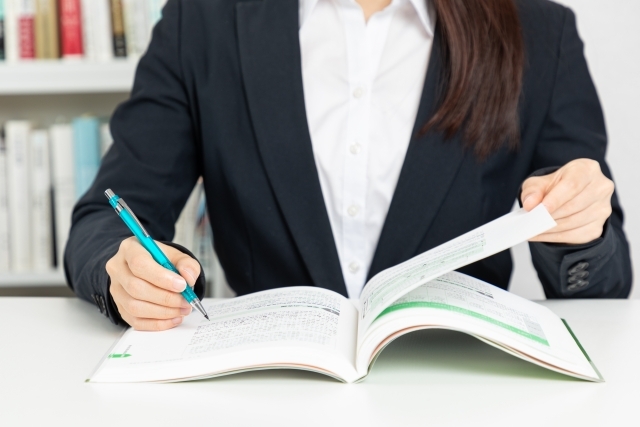会社の業務の特性に応じたルールや、会社が大切にしていることを守ってもらうことは重要です。いざというときには困った労働者にペナルティを与えられるように、就業規則の条文を工夫して記載する必要があります。
今回は、懲戒処分の特徴や注意すべきポイントについて考えてみましょう。
1.原則として、書いてあることでしかペナルティを与えられない
「こういうことをしたら、こういうペナルティがありますよ」ということが就業規則に記載してある必要があります。これは、刑法の「罪刑法定主義」と同じ考え方です。あらかじめ何をしたらいけないのかということがわかっていないと、自分のする行為が問題のある行為かどうかの判断ができないからです。
2.ペナルティの重さ
「やらかした事とペナルティのバランス」も重要です。たとえば、「遅刻1回で懲戒解雇」という処分は明らかにペナルティが重すぎますので、就業規則にこのような記載があったとしても、争われれば無効とされてしまうことになります。
3.他の人とのバランス
Aさんの懲戒処分をする際に、以前にBさんがAさんと同じような問題行動をしていて「減給」という懲戒処分であったときに、Aさんは「懲戒解雇」というのは公平性の観点から問題になります。4.私生活上の問題行動
判断が難しいのが、私生活上の問題行動です。私生活上でトラブルを起こしたり、法違反をしたとしても、あくまでプライベートでのことです。必ずしも、企業秩序を乱したり、会社に損害を与えたということにはなりません。その場合、懲戒処分の対象とするのは難しいことになります。
しかし、その問題行動によって会社名が新聞報道されたりすれば、会社の信用が傷つくことになりますので、その場合は処分が可能ということもあります。
5.弁明の機会の付与
懲戒処分を行なう際には、原則として「弁明の機会」を付与する必要があります。あくまで「対象者」の弁明の機会なので、懲戒処分の検討をしている対象者が嘘をついたり言い訳をしたとしても、叱ったり諭したりせず、対象者の話を聞くということが必要です。
6.その他
1つの事案で2重の処罰はできませんし、後からできたルールを遡り適用して処罰することもできません。また、問題行動が起きてからかなりの時間が経過した後の懲戒処分は、企業秩序の維持という点で相当性がないとされることもあります。懲戒処分の種類については下記のとおりです。
【よく見られる懲戒処分の種類】
| 譴責(けんせき) | 「始末書を提出させて、戒める」 始末書の提出を強要することや、反省を強要することは、憲法の「思想・良心の自由」を不当に制約することにもなりますので注意が必要です。 |
| 減給 | 「給与の一部を支給しない」 労働基準法に「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」という定めがあり、金額としてはたいしたことがないといえます。 ただし、労働をしたにもかかわらず、その賃金の一部が支払われないという非常に例外的な取扱いとなります。 |
| 出勤停止 | 「一定期間の出勤を禁止する」 出勤停止の期間は賃金が支払われません。期間があまりに長いと解雇と同様の意味となりますので、期間は1~2週間程度で定めていることが多いと思います。もっと長い期間の出勤停止として、「懲戒休職」という定めをしているところもあります。 |
| 降格 | 「職位などを引き下げる」 懲戒処分による降格は、人事権による降格とは別の扱いになります。 |
| 諭旨解雇(ゆしかいこ) | 「退職届の提出を促して提出されれば退職扱いとし、そうでない場合は懲戒解雇とする処分」 問題行動が懲戒解雇相当であっても、それまでの貢献や情状酌量の余地に配慮して使われる、懲戒解雇より少しマイルドな取扱いです。 |
| 懲戒解雇 | 「会社が一方的に労働契約を解約する処分」 懲戒処分で最も重い処分です。ただし、懲戒解雇であっても、解雇予告は必要です。労働者に帰責理由がある場合、労働基準監督署による「解雇予告除外認定」を受ければ、解雇予告手当の支払いが免除されます。 |
また、懲戒処分の書き方にも、次の3つの方法があります。
|
①懲戒処分の種類ごとに問題行動を記載する |
|
②ざっくり書いて、問題行動の程度で懲戒処分を決定する |
|
③重い懲戒処分(懲戒解雇、諭旨解雇)と軽い懲戒処分(降格以下)で書き分ける |
懲戒処分を実施することはないに越したことはありませんが、いざというときには“使える規程”にしておく必要があります。様々な要素があり、簡単ではありませんが、ぜひ新しい視点で見直しをしてみてくださいね。