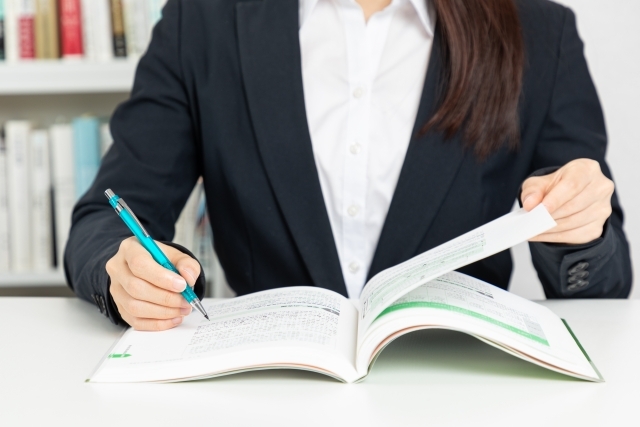労働時間の状況把握とは
これまで労働時間の把握義務については、労働基準法を根拠に適正な割増賃金の支払を目的とした指針「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省)がありました。このガイドラインでは、その目的から管理監督者やみなし労働時間制(裁量労働制や事業場外労働)の適用者は対象外とされていました。
今回、労働安全衛生法の改正により、健康管理の観点から、管理監督者やみなし労働時間制の適用者を含め、すべての人の労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法で把握することが義務化されます。
労働時間の状況を客観的に把握することにより、長時間労働者に対する医師の面接指導を確実に実施することができます。
労働時間の状況を把握する対象者は
健康確保措置を適切に実施するため、すべての労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません(2019年4月から開始となる高度プロフェッショナル制度の適用者を除く ※1)。※1 高度プロフェショナル制度の適用者には、別途、労働基準法により健康管理時間の把握義務があります。
つまり、管理監督者、みなし労働時間制(裁量労働制、事業場外労働のみなし労働時間制)の適用者、時間外労働の適用除外となる研究開発の業務従事者も含めて、すべての労働者が対象だということです。
労働時間の状況とは何を把握すればよいのか
平成30年12月28日付の行政通達(基発0907第2号)によれば、労働安全衛生法による労働時間の状況の把握とは、労働者の健康確保措置を適切に実施する観点から、“労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったかを把握するもの”とされています。具体的には、客観的な方法その他適切な方法により、“労働者の労働日ごとの出退勤時刻や入退室時刻の記録等”を把握しなければならないとされています。
この労働時間の把握は、労働基準法による賃金台帳への労働時間数の記入をもって、これに代えることができるとされています。これは、毎日の労働時間が適正に把握されていることが前提となりますが、割増賃金の一部対象外となる管理監督者やみなし労働が適用される者については、把握すべき労働時間の実態が賃金台帳には記入されていないため、別途の把握が必要となります。
客観的な把握方法とは
上記行政通達によれば、労働時間を把握する方法としては、原則として、タイムカード、パソコン等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録、管理職の現認等の客観的な記録等により把握しなければならないとされています。その他適切な方法とは
やむを得ず客観的な方法により把握しがたい場合は、労働者の自己申告による把握が考えられます。この場合は、自己申告により把握した労働時間と実態の労働時間の状況が合致しているか必要に応じて実態調査を行い、労働時間の補正をすること等が求められます。なお、行政通達によれば直行直帰の場合であっても、事業場外から社内システムにアクセスできる状態であったり、客観的な方法によって労働時間を把握できたりする場合は、直行直帰のみを理由とした自己申告による把握は認められないとされていますから注意しましょう。
労働時間の状況の記録の保管(3年間保存)
労働時間の把握に加え、客観的な方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。また、労働時間の記録・保存の方法については、紙媒体のほか、磁気テープ、磁気ディスクその他これに準ずるものに記録・保存することでも差し支えないとされています。
会社の対応
時間外手当を支払う一般の労働者については、従来から適正な労働時間の把握が実施されていましたが、同じ方法で管理監督者やみなし労働時間制の適用者についても労働時間の把握が必要となりました。裁量労働制の適用者は、健康確保措置の観点から労働時間相当の時間は把握していたものと考えられますが、管理監督者や直行直帰の場合の取扱いを含め、改めて客観的な把握方法を検討してみましょう。