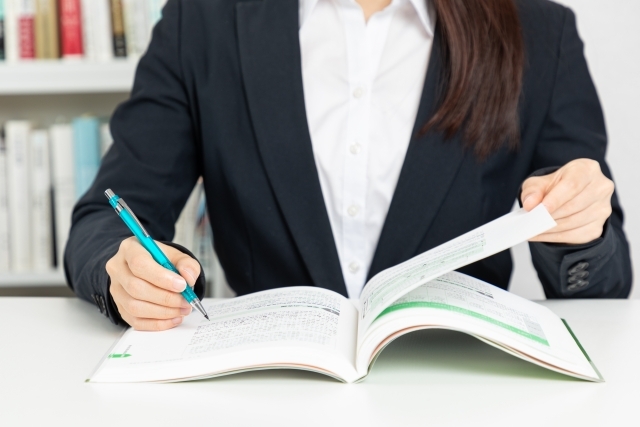法務省や経済産業省なども、このような動きに対応して、以下の「押印に関するQ&A」と「電子署名に関するQ&A」を公表しています。
そこで、これらの内容を踏まえつつ、2回に分けて、押印の法的な意味や、電子署名を利用した電子契約を導入する際の留意点などについて紹介します。
・内閣府・法務省・経済産業省「押印に関するQ&A」(令和2年6月19日)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ouin_qa.html
・総務省・法務省・経済産業省「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法2条1項に関するQ&A)」(令和2年7月17日)
https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei_qa.html
・総務省・法務省・経済産業省「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法3条に関するQ&A)」(令和2年9月4日)
https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei3_qa.html
契約書などの文書への押印の法的な意味
契約の成立に押印は必須ではない
保証契約などの一部の契約を除いて、契約は、当事者の意思の合致があれば、口頭でも成立し、契約書の作成や契約書への押印が必須というわけではありません(「押印に関するQ&A」Q1)。契約書への押印の有無によって、契約の効力の強さなどが変わるということもありません。なお、契約書の作成と契約書への押印は必須ではありませんが、当事者間において契約書の作成と契約書への押印が予定されている場合には、契約書へ押印された時点が、両当事者の意思の合致が成立した時点、すなわち、その契約が成立した時点である場合が、事実上多いでしょう。
文書への押印は「成立の真正」を立証する手段
契約書に限らず、納品書、請求書、領収書など、民事訴訟において文書を証拠とする場合、その文書が、文書の名義人によって作成されたものであること(つまり、何者かがなりすまして文書を作成したものではないこと。これを「成立の真正」といいます)が必要となり、民事訴訟の相手方が成立の真正を争った場合には、これを立証する必要があります。その際、文書への押印が存在する場合には、民事訴訟法の規定により、成立の真正が推定されます(「押印に関するQ&A」Q2)。
法的な観点からは、文書へ押印してもらうことの実益は、主として、成立の真正の立証のためであるといえます。
文書への押印を不要とすることは可能か
以上のとおり、文書へ押印してもらうことは有用ではありますが、その効果には限界もあります(「押印に関するQ&A」Q4、5)。たとえば、成立の真正の推定を受けるには、文書の名義人による押印がなされたこと、その前提として文書にある印影と名義人の印章が一致していることが必要ですが、押印されたものが、実印ではなく認印や角印の場合には、その立証が容易ではない場合もあります。
そのため、たとえば、重要度が高くない文書については、成立の真正の立証は、押印以外の手段によって確保することとして、押印は不要・文書を電子的に送受信するという取扱いを相互に行なうことも考えられます。
その場合、文書の成立の真正の立証の手段を確保するため、たとえば、以下のような措置を講じておくことが考えられます。
・文書を送受信した際のメールを保存しておく
・文書の成立過程で行なわれたメール等のやり取りを保存しておく
・文書をメールで送信する際に、相手方の担当者に加えて、相手方の決裁権者も宛先やCCに含めておく
押印の代替手段としての電子署名
特に契約書などについては、押印の代替手段として、電子署名を利用することも考えられます。電子署名に関しては、近時、従来から存在する「当事者型」ではなく、「立会人型」(クラウド型)などと分類されるサービス、すなわち「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行なう電子契約サービス」が広まっています。そのようなサービスに関して見解が示されたものが、前述の「電子署名に関するQ&A」です。
次回は、これらの内容も踏まえて、電子署名を利用した電子契約を導入する際の留意点などについて紹介します。